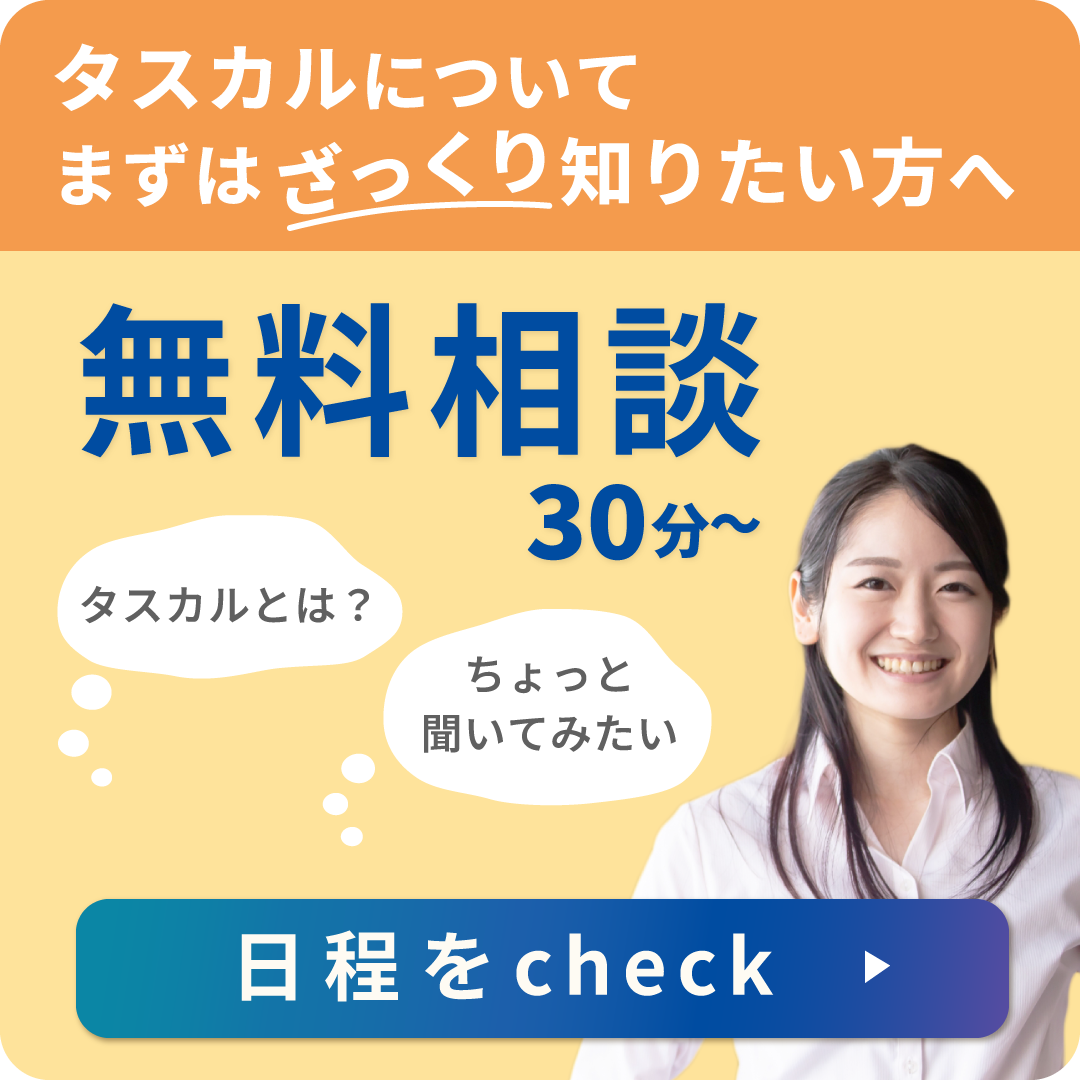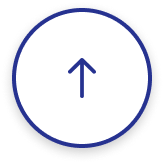小さな会社ほど、労務管理は「後回しにしがち」な業務です。勤怠集計に時間を取られ、有休の日数を正確に把握できず、気づけば法令違反のリスクを抱えている……そんな状況は決して珍しくありません。しかし、こうした問題を放置してしまうと、従業員の不満や行政からの是正勧告につながり、経営に思わぬ影響を及ぼすこともあります。そこで注目されているのが、労務管理システムの導入です。
本記事では、一人社長や中小企業経営者が直面しやすい労務の課題を整理し、システム導入によってどのように解決できるのかを具体的に解説。さらに、数あるサービスの中から特におすすめの7つを厳選して紹介します。
\はじめてのアシスタントサービスなら、月額2.75万円〜の「タスカル」🤗/
オンラインアシスタント「タスカル」は、経理や事務作業、Web・SNS更新などを丸投げOK!初期費用なし&低コストの月額で始められるので、一人社長やフリーランスに選ばれています。
小さな会社こそ注意したい労務の落とし穴
小規模な会社ほど、人事や労務の担当を専門に置けず、経営者や事務担当が兼務するケースが多いものです。その結果、「つい後回しにしてしまった」「気づいたらルールを守れていなかった」といったトラブルに発展することもあります。ここでは、特に一人社長や中小企業で起きやすい労務の落とし穴を整理します。
勤怠の集計に時間がかかる
勤怠管理を紙の出勤簿やExcelで行っていると、毎月の集計作業に多くの時間を取られてしまいます。打刻漏れや残業時間の手計算が必要になり、締め日前は「本業より勤怠処理に追われる」と感じる経営者も少なくありません。人件費の計算ミスにつながるリスクもあるため、効率化が求められるポイントです。
有休の日数が把握できず「義務の5日」を守れない不安
年5日の有休取得義務は、従業員数に関係なくすべての企業に適用されます。しかし、紙やExcelでの管理では「誰がどれくらい取得したか」がすぐに分からず、気づいたときには未取得者が出ているケースもあります。これは法令違反となる可能性があり、是正勧告の対象になることもあるため、小さな会社でも軽視できません。
帳簿や書類がバラバラに保存されていて探せない
労働者名簿や賃金台帳、出勤簿などの法定帳簿は、原則5年間の保存が義務付けられています。ところが、紙のまま棚やキャビネットに保管していたり、データが担当者のPCに散らばっていたりすると、いざ必要なときに探し出せないことがあります。監査や労基署からの指導に対応できないリスクがあるため、記録の一元管理は小さな会社ほど重要です。
労務管理システムがあれば解決できること
「手作業が多くて面倒」「法令に対応できているか不安」といった悩みは、労務管理システムを導入することで大きく軽減できます。システムが自動で集計やチェックを行ってくれるため、ヒューマンエラーが減り、経営者や担当者の負担を大幅に減らせるのです。ここでは、システムを使うことで具体的にどんな改善が期待できるのかを見ていきましょう。
勤怠を自動で集計してミスを防げる
出勤や退勤をPC・スマホ・ICカードで打刻すれば、自動的に勤務時間が集計されます。残業時間や深夜労働も正確に計算されるため、手作業による入力ミスや計算間違いを防ぐことができます。締め日前に慌てて集計する必要もなくなり、経営者自身が本業に集中できる時間が増えます。
有休管理をシステムがサポートしてくれる
有休の残日数や取得状況はシステム上で一目で確認できます。「年5日の取得義務」を満たしていない社員がいれば自動でアラートが出るため、未取得を防ぎやすくなります。担当者が細かく確認する必要がなくなり、安心して法令対応ができます。
帳簿や書類を一元管理できる
労働者名簿や賃金台帳などの法定帳簿は、システム上で自動作成・保存が可能です。検索や出力も簡単に行えるため、監査や労基署からの調査依頼があってもスムーズに対応できます。バラバラに保管されていたデータを探す手間から解放されるのは、小さな会社にとって大きなメリットです。
自社に合ったシステムを選ぶポイント
労務管理システムは種類が多く、「どれを選べばいいのわからない」と迷う経営者も多いです。すべての機能を備えた高機能システムは魅力的に見えますが、小さな会社にとってはオーバースペックになりがちです。大切なのは「自社に必要な機能は何か」を整理してから選ぶことです。ここでは、導入前に押さえておきたいポイントを紹介します。
働き方に合った勤怠管理方法を選ぶ
従業員が店舗勤務なのか、リモートワークが多いのかによって適した打刻方法は異なります。
- 店舗や現場が中心 → スマホやICカードでの打刻が便利
- オフィスやリモート中心 → PCログイン・ログアウト連動型がスムーズ
現場の状況に合わない仕組みを選ぶと、結局「使われないシステム」になってしまいます。
給与ソフトや会計システムとの連携を確認する
勤怠データや残業時間をシステムから給与ソフトに自動連携できれば、手入力や二重入力の手間を大きく減らせます。会計ソフトとも連携できれば、労務・給与・経理の流れを一気通貫で効率化できます。自社で既に使っているツールとの相性は必ずチェックしましょう。
料金体系と導入サポートを比較する
労務管理システムには「1ユーザーあたりの月額制」「固定料金制」などさまざまな料金プランがあります。小さな会社であれば、初期費用が低く抑えられるクラウド型を選ぶと安心です。また、導入時にどこまでサポートしてもらえるのかも重要です。設定や初期導入をサポートしてくれるプランがあれば、立ち上げもスムーズに進みます。
おすすめの労務管理システム7選
本記事では、特におすすめの労務管理システムを7種類紹介します。システムごとに、どのような企業におすすめかを以下に簡潔にまとめました。
- SmartHR 労務管理…一人社長や小規模企業で、ペーパーレス化や電子申請による業務効率化・法令遵守を手軽に進めたい企業
- freee 人事労務…転記や手入力を減らして、入社から給与・年調・給与明細までクラウドで一括管理したい中小企業
- ジョブカン 労務HR…入退社手続き、社会保険や年末調整などの労務業務をネット上で自動化し、手間を減らしたい企業
- KING OF TIME 人事労務…勤怠管理との連携で入社手続きや給与明細を含む人事業務をワンストップで管理したい企業
- ジンジャー人事労務…ペーパーレス化を推進しつつ、直感的な操作性で社内の人事情報をまとめて管理したい企業
- ARROW…シフト管理・勤怠・給与計算など労務業務をワンシステムで安価にまとめて運用したい店舗や小規模事業者
- サイレコ…従業員情報を一元管理し、人事評価やタレントマネジメントなど戦略的な人事運用に取り組みたい中〜大企業
SmartHR 労務管理

| 料金(税込) | 特徴 |
要問い合わせ |
|
SmartHR 労務管理は、入社から退社に至るまでのあらゆる労務業務をペーパーレス化し、業務効率と正確性を同時に高めるクラウド型ソフトウェアです。入社手続きや雇用契約、年末調整、マイナンバー管理といった煩雑な業務を、すべてデジタル画面上で完結できます。帳票の自動生成やe‑Gov連携による電子申請にも対応。SmartHRは頻繁に機能アップデートが行われており、小規模事業者でも安心して法令遵守を続けられる設計になっています。
freee 人事労務

| 料金 | 特徴 |
給与計算機能なし 1,500円/月~ |
|
freee人事労務は、紙やExcelに頼っていた労務業務を“まとめてクラウド化”し、入社手続きから給与計算、年末調整、WEB給与明細の発行に至るまで、一気通貫で効率化できる労務管理システムです。従業員情報や勤怠データが一元管理されているため、複数のシステム間で転記やデータ手動入力を行う必要が無くなり、“うっかりミス”や“対応漏れ”を防ぎます。更新対象者へのアラート機能が備わっており、入退社手続きの漏れや契約更新忘れも防ぎやすい設計です。完成した書類は電子保存できるため、保管や検索も容易です。
ジョブカン 労務HR

| 料金(税抜き) | 特徴 |
中小企業:400円/月(1ユーザーあたり)~ |
|
ジョブカン 労務HRは、入退社手続きや扶養変更、帳票作成といった労務業務をクラウド上で自動化・効率化できるシステムです。従業員情報の入力依頼や履歴管理が簡単に行え、関連書類は帳票テンプレートから自動生成され、e‑Gov対応で電子提出も可能です。さらに、ToDoリストや進捗管理機能によって「いつどこに何を出すか」が可視化されるので、労務担当が慣れていなくても、提出漏れの不安なく進行できます。シリーズ全体で累計25万社を超える導入実績があり、多くの中小企業やスタートアップ、一人社長の現場でも活用されています。
KING OF TIME 人事労務

| 料金 | 特徴 |
300円/月(1ユーザーあたり) |
|
KING OF TIME 人事労務は、勤怠管理・給与計算とセットで使えるクラウド型の人事労務統合システムです。帳票整備や申請のために複数ツールを使い分ける手間を解消し、追加費用なしで一つのシステムにまとめて対応できる点が大きな魅力です。1人あたり月額わずか300円(勤怠含む)という料金設計で、初期費用0円の無料体験から始められ、充実したサポート体制(チャット、電話予約制、オンラインヘルプなど)も整っています。
ジンジャー人事労務

| 料金(税込) | 特徴 |
要問い合わせ |
|
ジンジャー人事労務は、人事・労務・勤怠・給与・タレントマネジメントなどの業務を、1つの統合型クラウドプラットフォーム上で管理できる、統合型人事労務システムです。すべてのデータが Core HRデータベースに集約される設計により、定型業務の自動化がスムーズに行えます。さらに、従業員向けのポータル画面が刷新され、「よく使うメニュー」のワンクリックアクセスや、人事問い合わせAI機能による自動応答によって、操作負荷の軽減と人事担当者の負担削減が可能です。
ARROW

| 料金(税込) | 特徴 |
2,178円/月~ |
|
ARROWは、シフト作成、ICカードやGPSなど多様な打刻方法による勤怠管理、給与計算、給与・賞与明細作成、各種帳票の自動作成、年末調整までを一つのクラウドシステムで完結できる統合型労務管理システムです。特にUIには力が入れられており、誰でも直感的に操作できる画面構成となっています。さらに、無料トライアルが最大60日間利用可能で、月額利用料も小規模事業者に配慮した設定があり、導入の初期費用を抑えつつ試せる点も嬉しいポイントです。
サイレコ

| 料金(税込) | 特徴 |
250円/月~(1ユーザーあたり) |
|
サイレコ(sai*reco)は、組織人事に関するさまざまな情報をクラウド上に蓄積し、“使える人事情報”として活用するためのHRオートメーションシステムです。定型業務の自動化により、入力・承認・更新・給与計算などのルーチン作業を効率化できるため、担当者の時間を「戦略的な人事業務」へ振り向けられるようになります。さらに、組織図による異動シミュレーション、人事評価や研修の履歴管理、スキルや面談結果などのタレント情報の蓄積と分析も可能で、人材配置や育成計画など“戦略人事”を具体的に支える設計が魅力です。
導入までの流れとスケジュール感
労務管理システムは「とりあえず入れればすぐ便利になる」というものではありません。自社のやり方を整理し、必要な設定をきちんと行うことで、初めて“ラクになる効果”を実感できます。小さな会社であっても、3か月ほどを目安に準備を進めると無理なく導入できます。
1〜2週目:現状のやり方を整理する
まずは今どのように勤怠や有休を管理しているかを棚卸しします。紙やExcelでどんな表を使っているか、どの業務に時間がかかっているかを把握することで、システムに「何を任せたいか」が明確になります。
3〜6週目:システム選定と初期設定を行う
候補となるシステムを比較し、デモを試して操作感を確認します。そのうえで導入するサービスを決め、従業員情報や勤務ルール(就業規則に基づく勤務時間や休憩時間など)を登録していきます。初期設定は専門用語が多く戸惑うこともあるため、サポートが手厚いサービスを選んでおくと安心です。
7〜10週目:テスト運用で慣れる
全社員に一気に使わせる前に、まずは一部のチームや部署で試験的に運用してみましょう。実際に打刻や有休申請を行い、問題点や分かりにくい部分を洗い出します。
11〜12週目:全社で本格稼働
テストで得た改善点を反映し、全社員に利用を広げます。あわせて、給与ソフトや会計システムとのデータ連携も本格的に回していくと、導入効果をすぐに実感できます。
導入後に気をつけたい運用のコツ
労務管理システムは導入して終わりではありません。正しく運用を続けていくことで、はじめて「労務の不安から解放された」と実感できます。ここでは、導入後に押さえておきたいポイントをまとめます。
月ごとのチェックを習慣化する
毎月の締め処理では、打刻漏れや残業時間の超過がないかを必ず確認しましょう。システムが自動でアラートを出してくれる場合でも、人が最終確認をすることでミスを防げます。ルーチンとして月次チェックを組み込んでおくと安心です。
年単位で法改正に対応する
労務関連の法律や制度は定期的に改正されます。たとえば有休の取得義務や社会保険の適用拡大などは、企業規模に関係なく影響を受けます。年に一度はシステムの設定や運用を見直し、最新のルールに対応できているか確認することが大切です。
属人化を防ぐ仕組みを作る
「この人しか操作方法を知らない」という状態はリスクになります。マニュアルを作成したり、担当者を複数人に分けたりして、誰でも基本操作ができる体制を整えておきましょう。担当者が変わってもスムーズに引き継げる仕組みがあると安心です。
効果を数字で実感する
導入後は「勤怠集計にかかる時間が半分になった」「年休の未取得者がゼロになった」など、数字で成果を振り返ると効果を実感しやすいです。効果が目に見えると、経営者だけでなく従業員の満足度も高まり、システムの定着につながります。
労務管理システムで日々の負担を減らし、本業に集中しよう
労務管理システムは、勤怠や有休管理、入退社の手続きなど、煩雑でミスが起きやすい業務を自動化し、スムーズに進めるための心強いツールです。もちろん、システムを入れるだけではすべての負担がゼロになるわけではありません。初期設定や運用の見直しには一定の手間がかかりますし、「誰が操作するのか」「法改正にどう対応するか」といった体制づくりも欠かせません。そうした部分をカバーする方法として、オンラインアシスタントサービスを活用するのも有効です。
たとえば「タスカル」のようなオンラインアシスタントサービスでは、労務システムの導入サポートや日々のデータ入力・確認作業を任せることができます。自社で人を増やす必要がなく、必要なときに必要な分だけサポートを受けられるため、限られた人員で運営する中小企業にとって心強い存在になるでしょう。
参考:事例に学ぶ!医療機関におけるDXコト始め | 勤怠・労務ソリューションを起点に「攻め」の人事戦略を見据える|コトセラ